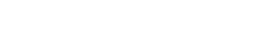こんにちわ。ニコデンタルクリニック院長の西野です。
今回は口臭についてお話します。
口臭の原因の80%はお口の中にあるといわれています。
歯周病、清掃不良、虫歯、舌苔、口腔乾燥(ドライマウス)などが口の中からくる口臭の主な原因です。
他にも糖尿病や呼吸器系の疾患、腎不全、副鼻腔炎などの全身疾患からくる口臭もあります。
口臭には病気からくるものだけでなく起床時や空腹時には誰でも口臭が強くなる傾向があります。
これらを心配なさって来院される方も多くいらっしゃいますが、これは生理的口臭といって誰もがあるものでありゼロにはできませんし問題ありません。
効果的な口臭ケアの方法として舌苔の除去があります。
舌苔は舌の表面に付着する白い苔のようなもので舌苔の清掃は口臭予防に非常に効果的です。
舌の奥から手前にかき出すように優しく繰り返しこすります。
この時前後にこすると誤嚥の原因になるため手前にかきだします。舌はデリケートな組織なので、柔らかい歯ブラシか専用の舌クリーナーで優しくお掃除することをおすすめします。
口腔内を清潔に保ち、お口のクリーニング、検診を定期的に受けることが口臭予防にも効果的です。